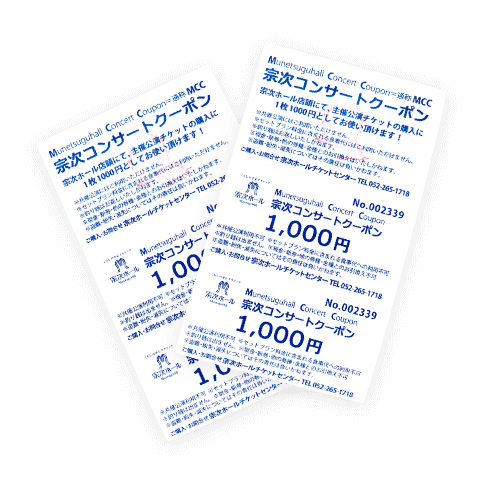竹澤恭子 J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル 第1回
2025年
11/15
(土)
14:00開演
13:30開場
- 出演者
- 竹澤恭子(ヴァイオリン)
- 曲目
- J.S.バッハ:
ソナタ 第1番 ト短調 BWV1001
パルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002
ソナタ 第2番 イ短調 BWV1003
※2公演セット券…8,000円

「祈りと魂とともに ~ バッハ無伴奏への旅」
バッハと向き合うこと̶̶それは、私自身のこれまでの音楽人生と向き合うことでもあると感じています。
幼い頃からバッハは、私にとって比較的身近な存在でした。ガヴォットやメヌエットなど、自然と心の中に入ってくるような親しみやすい音楽であり、チェリストのパブロ・カザルスによる《無伴奏チェロ組曲》は、幼い私にとって特別な愛聴盤でした。
時が経ち、多くの作曲家の作品に触れ、演奏経験を重ねるなかで、私は次第にバッハの音楽の持つ世界観の大きさを実感するようになりました。時代を超えて、数えきれないほどの作曲家たちがバッハから深い影響を受けていることも、自然と腑に落ちていきました。そして、その偉大なバッハの音楽と真剣に向き合うことが、どれほど大変で重いものであるかを感じれば感じるほど、自分の未熟さを痛感し、なかなかその一歩を踏み出す勇気が持てずに、悶々とした日々を過ごしてきました。「自分は芸術家として、果たしてバッハに向き合う力があるのか?」その問いは、長らく私の心の中にあり続けていました。けれども、これまでの音楽経験を重ね、そしてヴァイオリンに限らず、さまざまなアーティストたちによる多彩なバッハ演奏に触れるうちに、ようやく今、自分自身の心に響くバッハ像というものが、少しずつ見え始めてきました。
《無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ》に取り組むことは、技術的にも、音楽的にも、そして精神的にも極めて高い壁を伴う挑戦です。対位法を含む多声音楽を一つの楽器で表現するという構造的な困難、壮大な音楽の構成感、舞曲形式のスタイルやバロック音楽の文法の理解̶̶そのすべてが、ひとりの演奏家に深い洞察と覚悟を求めてきます。それでも今回、私は思い切ってこの挑戦に臨むことを決めました。それは、自分の中にこれまで培ってきた音楽経験、そして人生経験のすべてを注ぎ込むことで、私自身の人生観が映し出されるようなバッハを、皆様にお届けできたら̶̶と、そう願っているからです。それは、幼い私が夢中になって聴いていたカザルスのバッハから受け取った、魂の声、祈りの心が、今も私の中で根を張り、生き続けているからにほかなりません。
永遠なるバッハの音楽には、人と人との心をつなぐ力があると、私は信じています。
竹澤恭子(ヴァイオリン)Kyoko Takezawa ‒ Violin
桐朋女子高校音楽科在学中に第51回日本音楽コンクール第1位を受賞。1986年第2回インディアナポリス国際ヴァイオリン・コンクールで圧倒的な優勝を飾る。
これまで、ニューヨーク・フィル、ボストン響、モントリオール響、ロンドン響、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、ロイヤル・コンセルトヘボウ管等と、また、マズア、メータ、デュトワ、小澤征爾他、多くの名指揮者とも世界の檜舞台で共演している。
2011年にはフィルハーモニア管のスペインツアー、2012年にはハンブルク北ドイツ放送響の日本公演でソリストを務め、2014年には東京フィル100周年記念ワールドツアーのソリストを務め、パリ、ロンドンなどで高い評価を得た。2018-2019年シーズンは、デビュー 30周年を迎え各地でリサイタルを行い好評を得た。
また、才能教育研究会で学んだ経験を生かし、教育活動も行い、メニューイン、ロン=ティボーなど国際コンクールの審査員も数多く務める。また、アスペン、ルツェルンといった世界的な音楽祭にも出演を重ね、最近では水戸室内管弦楽団、セイジ・オザワ松本フェスティバル、別府アルゲリッチ音楽祭へも参加。協奏曲、室内楽、リサイタル等、幅広く活躍を続けている。
1993年出光音楽賞、1999年度愛知県芸術文化選奨文化賞、2021年大府市民栄誉賞、2025年第78回中日文化賞を受賞。
使用楽器は、1724年製アントニオ・ストラディヴァリウス。
現在、東京音楽大学教授、桐朋学園大学特任教授、洗足学園音楽大学客員教授。
☆下記公演もございます。
2025年11月29日(土)14時開演「竹澤恭子 J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル 第2回」
【曲目】
J.S.バッハ:
パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006
ソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005
パルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004